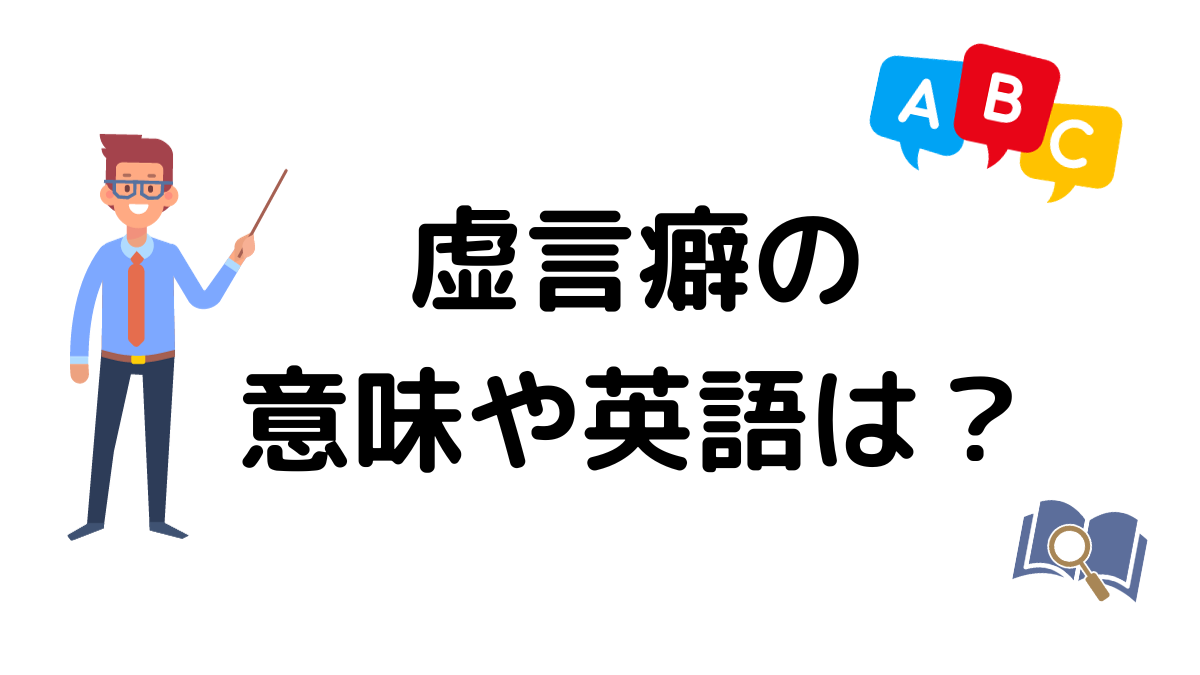本記事では虚言癖の意味と、英語では何て言うのかを、複数の辞書から調べた結果をまとめています。
嘘偽りのない幸せを手に入れたくありませんか?
\電話占い・初回3000円クーポン付き/
\気軽にチャット相談/
虚言癖の意味について

「虚言癖」とは、どうしても嘘をつく人の性質を表す言葉です。
1891年にドイツの心理学者アントン・デルブリュックによって提唱されたものです。
辞書における「虚言癖」
実は、広辞苑などの辞書に「虚言癖」という単語は載っていません。私が探せる限りどの辞書にも単語としての記載はありませんでした。(執筆日時点)
大体の辞書には「虚言」の意味が載っていて、たまに使用例として「虚言癖」が載っているくらいです。
虚言=他人をあざむく言葉。うそ。そらごと。虚語。きょごん。
(広辞苑より)
なので、虚言癖は「虚言」+「癖」という造語で、文字通り嘘を言ってしまう癖という意味になります。
辞書に記載があるのは「虚言症」
広辞苑には「虚言」の欄に派生として「虚言症」や「空想虚言症」についての記載があります。
虚言症=過去の事実、自己の境遇などを空想的に潤色・変形し、自ら虚言と現実とを混同する病的な精神・心理状態。自己顕示的あるいはヒステリー的性格異常者に見られる。空想性虚言。
(広辞苑より)
そして、大辞林ではこのような記載です。
虚言症=精神症状の一。意識的に,あるいは空想的にうそをつくもの。顕示性性格によるものや,躁状態・健忘症などによる病的虚言などがある。
(大辞林より)
虚言症の「症」は病気の症状を表すので、虚言症になると病的なものになります。
虚言癖と虚言症は紙一重ではあるかもしれませんが、言葉の使い方的には、病的まで行かないのが虚言癖です。
虚言癖の読み方
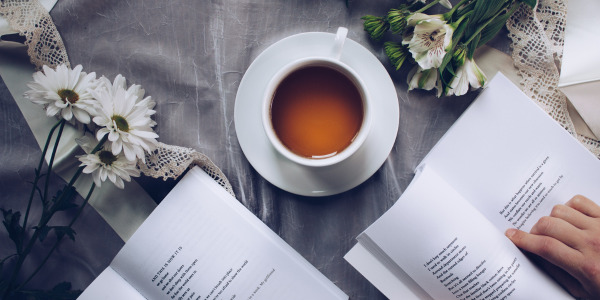
虚言癖は「きょげんへき」と読みます。
嘘を指す「虚言」も一般的には「きょげん」と読みますが、「そらごと」「きょごん」「むなごと」と読むこともできます。どれも意味は同じになります。
虚言には色々な読み方はあるものの、虚言癖は「きょげんへき」という1種類の読み方しかありません。
虚言癖を英語で言うと?

虚言癖を英語で言うと、「Pathological liar/lying」(病的な嘘付き)が有名ですが、様々な言い方があります。
日本語での虚言癖は、「ただ話を盛り続ける人」「病的に近い嘘を言い続ける人」など幅広い意味を一つの単語で使っている気がします。
英語だとどのような表現になるのか、辞書での慣例も含めてまとめていきます。
他の言語はこちら

「ジーニアス和英辞典」での虚言癖
ジーニアス和英辞典では、「虚言癖」について以下のような記載があります。
虚言癖=compulsive [habitual] lying
彼女は虚言癖がある=She is a compulsive [habitual] liar.
(ジーニアス和英辞典より)
“compulsive”は「強迫観念にとらわれた、何かをせずにいられない」と言う意味の形容詞なので、嘘つかずにはいられない=虚言癖になります。
もう一つ示されている“habitual”は、「習慣的な、常習的な」と言う意味の形容詞です。こちらは理解しやすい単語です。
ちなみに、NHKの語学フレーズ紹介では、以下のように書かれていました。
She’s a liar.
それは、虚言癖。
つまり、ただの「嘘つく人」として表現されていました。
心理学の専門用語としての「虚言癖」
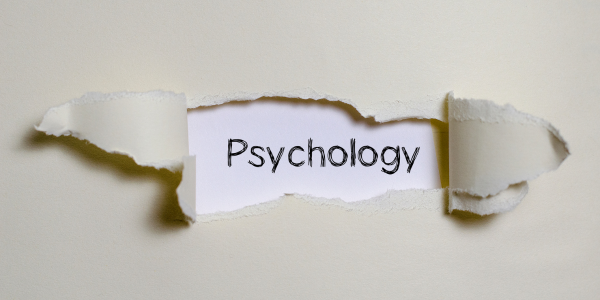
和英辞典や英和辞典を調べた結果、専門用語としては「虚言症」と「虚言癖」2つの単語がありました。
「虚言症」=mythomania
「虚言癖」=mendacity
(新英和中辞典より)
さらに、英語の語源から解説すると
” -ia “は病気を表す単語にくっつきます。
例:insomnia=不眠症、anorexia=拒食症など
“ -ity “は「〜である状態・質」を表しています。
例:accessibility=アクセスできる、近づきやすさなど
というようになります。
厳密に言えば、心理学用語であるのが ” mythomania “で、嘘をつくことを意味する名詞が ” mendacity “です。
専門用語になると難しいので、一般的に日本語で言う「虚言癖」はcompulsive [habitual] lyingやPathological liar/lyingになるでしょう。
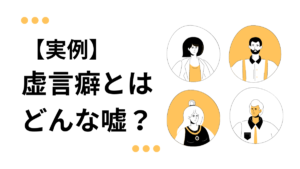
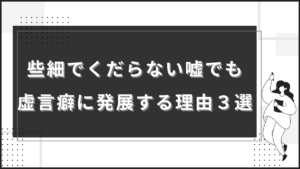
嘘偽りのない幸せを手に入れたくありませんか?
\電話占い・初回3000円クーポン付き/
\気軽にチャット相談/